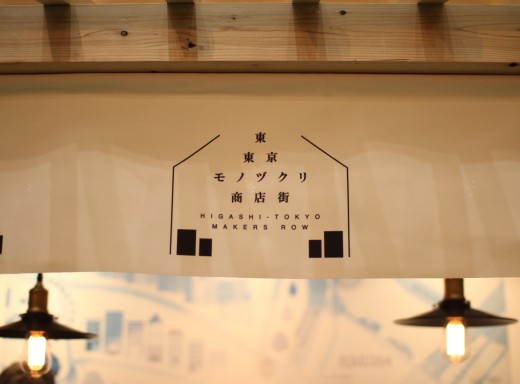古来より、大切なものをしまう収納具として活用されてきた桐箱。箱義桐箱店は、1868年からこの桐箱を手掛けてきた老舗だ。
「今でこそ高級な骨董品や美術品を入れる収納品と思われていますが、昔はもっと身近で、さまざまな日用品を収める箱として使われていました」と、桐箱の経緯について語るのは、6代目にあたる戸張茂義代表取締役だ。物心が付く前から家長であり職人だった祖父が桐箱を作り上げていく様子を間近で見ていて、小学校の卒業文集には「日本一の桐箱屋になる」と書き記していたという。

「昭和40年代は、万博やオリンピックの徽章を収める箱として沢山の需要がありました。さらに、当時は退職や長期勤続の記念品として杯を贈る文化があり、そのための箱も求められていました。そこで1970年には広島に工場を設立して、量産体制を構築したんです。今だと信じられないような話ですけど、桐箱をクルマの荷台いっぱいに積んで銀器屋さんや徽章屋さんへ収めにいっても足りずに、一日2~3回往復しものでした」
当時のような激しい需要はしだいに収束し、今では徽章屋への納品も1週間に1度で充分だという。

徽章や記念品の需要が低減したものの、桐箱の売上も同じ具合に下がったわけではなかった。収納具である桐箱は、人々が注目し、必要とされているモノが美しく収まるよう、形を自在に変えられる商材だ。
「『盛者必衰』と断じるわけじゃありませんが、やはり人気のピークがあれば衰退もあります。私どもには北は北海道から南は九州まで約4000の取引先があり、柔軟に対応させていただくことで堅実な経営を維持させていただいております」

幅広い業種の取引先とつながりを持つことで市場動向に敏感になり、売上の推移をある程度予見できるようになった。生き残れる企業の条件のようなものも見えてきたと茂義さんは話す。
「かつての仏具ブームで売上が増した銀器屋さんは、需要が軽減したのちにインテリア業界に参入して新たなチャンスを掴まれていたり、また一時大盛り上がりした江戸切子屋さんも、若手や海外のデザイナーとのコラボを打ち出して別の魅力を提案したりと、力強く生き残っている企業は技術に加えアイデアもお持ちで、それを行動に移していらっしゃる。同じ中小企業として、とても勇気がわきます」

150年以上の歴史に裏打ちされた技術力に加え、全国にまたがるネットワークの広さが箱義桐箱店の強みだ。
「他社の多くは地方にある窯元の近くに拠点を構え、その地で作られる陶芸品の収納を主事業とされています。しかし当店は東京に小売店を持ち、業社さんはもちろん一般消費者の方とも対面販売を通じてご要望をお伺いして、臨機応変に対応させていただいております」

収納する器である桐箱は、中に入れるモノがなければ成り立たない。既製品で用が足りればいいが、そうでない場合は最適な形にアレンジさせる必要がある。そうしたやり取りが、新たな定番品を生み出していく。
「人気商品に『手入れ具』というのがあるのですが、もとは刀の手入れ道具を収納する箱でした。今はそんな道具を使う人なんていませんから、中仕切りも取ってしまったのですが、いろいろな物を入れやすいとよく売れるんです。他にも二つ折り財布を収納していた『二つ折り』とか1本用の燭台入れだった『一本立て』とか、400ほどの既製品がある。製品名を見るだけでも、日本で売れていたモノの歴史がわかるんですよ」
他業界にもれず、一時は安価な中国製品が市場に出回ったこともあった。しかし、商品設計や数量・納期など顧客のニーズにきめ細かく対応することのできる箱義桐箱店は中国製品に打ち負けることはなかった。

大事なモノを収納する製品として黒子役をこなしてきた一方、「大切なモノをしまいたくなるような桐箱」も提案している。
へその緒を保管する箱として、縁起のいい八角形やハート型、生まれ年の干支を描いた製品を展開。日本の浮世絵や伝統柄をUV印刷した製品は海外観光客にも人気だ。東東京モノヅクリ商店街への参画も、これまでにない魅力的なオリジナル製品の開発を求めての行動だった。
「ここ数年で海外の展示会にも出品するようになり、シンガポールとタイでの取り扱いをはじめたところ、想像以上の好感触を得られました。今後を考えるとやはり国内だけではジリ貧になってしまう懸念がありますから、国内のインバウンドや海外への展開をさらに積極的に取り組んでいくつもりです」

日本の伝統文化と強いつながりを持つ桐箱には、調湿機能や防虫機能といった実用面を超えた魅力が備わっている。そこが海外での勝機につながる。さらには、現代の日本人にも今一度感じてもらいたい部分でもある。
「私どもの製品を通じて、桐箱のよさをもっと知っていただいて、普段遣いしてもらえたらうれしいですね」